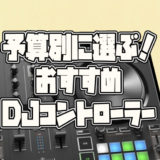シンセサイザーとは
シンセサイザーは、音と音を合成して新たな音を作り出す楽器になります。
シンセサイザーでは、鍵盤楽器のほか、ベースやギター・和楽器などさまざまな音色を作り出すことができるので、極めることができればどんな音でも作ることができるでしょう。
ただ、シンセサイザーを触ったことがない方には、ツマミが多く機能が多いため、どう言うふうに音を作れば良いのかわからないのも事実です。
音色の多いシンセサイザーを学習し、自分で扱えるようになることで、自分の曲をはなやかにしていきましょう。
最近ではパソコンにつないで音を作ったり、楽曲制作をしたりと幅広く使うことができるので、1台持っていても損はないでしょう。
シンセサイザーとキーボードって何が違うのか?

シンセサイザーとキーボードってどう違うのか疑問に思ったことはありませんか?
キーボードは、単体でも音がなりますが、シンセサイザーではヘッドホンなどを接続して音を出します。
手軽に鍵盤楽器を楽しみたい方はキーボードを、DTM(Logic ProやGarageBand)などでさまざまな音色演奏したい方はシンセサイザーと使い分けてみてはいかがでしょうか。
MIDIキーボードとキーボードはまた違うので、そこも注意してください。
MIDIキーボードも単体での音は鳴らないのでパソコンとつないで音を出す必要があります。
ここではMIDIキーボードについてはこのくらいにしておきますが、それぞれの鍵盤楽器を購入するときには、使う用途を十分に考えて、適切な鍵盤楽器を購入するようにしましょう。
シンセサイザーの選び方
シンセサイザーを選ぶときに特に注意しないといけない点や、おすすめのシンセサイザーを紹介していきます。
鍵盤の打感
鍵盤をタッチしたときに勢いよく鍵盤が下がってしまったり、鍵盤を押したときに硬かったりすると大変弾きにくいものです。
自分の演奏スタイルに合わせて打感を確認し、疲れにくい打感のものを選ぶのも良いかもしれません。
少しのタッチで鍵盤が下がるものも、音色を録音するときなどに誤って弾くと、ミスタッチまでも録音されることになります。
その辺りを確認しながら鍵盤の打感を確認していきましょう。
ツマミやボタンの数
シンセサイザーを選ぶときに、ツマミの数やボタンの数などがどの程度備わっているのかを確認しましょう。
中には、色とりどりの光を放つボタンなどもあるので、暗いライブハウスなどで演奏するときには、ボタンがどこにあるのかを見分けることができるので大変便利です。
ツマミを回して音色を変更するときに、ストレスなく演奏できる場所にツマミがついているのかなどもシンセサイザーを選ぶときには注意が必要です。
こればかりは実際に演奏してみて気づくこともあるので、神経質にならずに考えてみましょう。
鍵盤数
シンセサイザーの鍵盤数は25鍵から88鍵まで幅広い機種があります。
片手で演奏するのであれば25鍵でも十分演奏することができますが、両手で演奏したい場合には、48鍵以上のシンセサイザーが便利でしょう。
88鍵あれば、普通のピアノなどと同じになるので、幅広い演奏が可能になりますが、なにぶん大きくなるためデスクの幅を取るようになります。
せっかく購入したのに、机に収まらないとなると買った意味がないので、その辺りも購入のチェックポイントとしておさえておきましょう。
レイヤー機能
レイヤー機能は、重ねるという意味があり、音色と音色を重ね合わせて、別の音色を作る機能のことです。
例えば、ピアノとバイオリンの音をレイヤーすることで、一つの鍵盤を押すこと両方の音が同時に鳴るようになります。
レイヤー機能を使うことで、多彩なアンサンブルを作ることができ、楽曲にマッチする音を簡単に鳴らすことができるのです。
バンドなどでシンセサイザーのレイヤー機能を使って、足りない周波数帯域を補うこともできます。
単音でも音が太くなり、新しい音を作ることができるので、レイヤー機能を使ってみてください。
スプリット機能
スプリット機能とは、右手と左手で違う音を鳴らすことができる機能になります。
例えば、右手はベースの音を登録し、左手はギターの音を登録することで、両手でバンド演奏が可能になります。
また、バッキング(伴奏演奏)をやりながらリード楽器を弾くこともできるので、演奏の幅は広がります。
スプリット機能は、どんな音色でも登録することができるので、色々試してみるのも面白いかもしれませんね。
重量で選ぶ
持ち運びを頻繁にする人には、軽量のシンセサイザーを選ぶようにすれば、野外でも使うことができるでしょう。
自宅でレコーディングのみに使う場合は、重量が重くても機能が豊富な方が有利になる場合もあります。
購入する前には、必ず重量を確認し、使う用途に合わせたシンセサイザーを選ぶようにしましょう。
金額で選ぶ
シンセサイザーの金額は安いもので数千円のものから高いものになると何十万とする機種まであります。
金額をケチらずになるべく高いものを購入するのが良いのですが、何千円のシンセサイザーでも高いパフォーマンスを出してくれるものもあります。
金額が高くなると多彩な機能がついてきますが、逆に機能が多すぎて初心者には使いにくいかもしれません。
初めはなるべく機能の少ないものを購入し、慣れてきてから高価な機種に乗り換えるのも一つの方法ではないでしょうか。
おすすめシンセサイザー
ここからは、どのようなシンセサイザーを選べば良いのか、どういった商品があるのかを紹介していきます。
必ず自分の使いたい環境で動作できるのか、また、自分の使いたい機能があるのかなど確認して購入してください。
何万円もするシンセサイザーを購入して間違えてしまった場合には、取り返しのつかないことになるので、よく考えて購入を検討するようにしましょう。
ROLAND(ローランド)
JD-Xi

ハイブリッドシンセサイザーのJD-Xiは、37鍵盤のみにシンセサイザーになります。
持ち運びが便利なコンパクトボディで、アナログとデジタルの両方のサウンドエンジンを積んでいるため、両方の魅力を存分に味わうことができます。
多様なニーズに対応することができるので、環境にあったシンセサイザーサウンドを自分の手で作り込むことができるでしょう。
FA-06

音楽制作やライブ演奏、レコーディングなど幅広く使うことができるFA-06は、プロのミュージシャンやアーティストから絶大な支持を集めているため、値段相応のパフォーマンスを実現します。
カラー液晶画面を搭載しているので、暗いライブ会場などでもパラメータを操作できるので、大変重宝します。
初心者はもちろん、上級者にもおすすめするシンセサイザーになります。
JUNO-DSシリーズ

シンセサイザーのエントリーモデルJUNO-DSシリーズは、ライブやリハーサルなどの過酷な状況下でも対応することができる軽量シンセサイザーになります。
電池駆動対応のため、電源がない場所でも使用することがでくるメリットがあります。
多様な鍵盤数を取り揃えているため、自身の環境下にあった鍵盤数のDSシリーズを使ってみてください。
DS61は61鍵、DS76は76鍵、DS88は88鍵となっています。
TR-6S RHYTHM PERFORMER

40年以上にわたり、ローランドのリズムマシンTRシリーズはエレクトロニックミュージックに大きな影響を与えてきました。
その伝統を受け継ぎ、人気の高いTR-8Sを基に開発されたTR-6Sは、コンパクトな筐体に凝縮され、部屋を揺さぶり、人々を踊らせる力強いサウンドを持っています。
制作場所を選ばず、ハンズオンのプロダクションでビートメイキングを楽しんでください。
クラシックなサウンドから最新のトレンドまで、TR-6Sは未知のトラックを生み出します。
6つのトラックから生まれる至福のリズム。
TR-6Sはローランドの技術とエレクトロニックミュージックの歴史を結集し、バッテリー駆動可能なコンパクトな筐体に収めました。
親しみやすいステップシーケンサーとフィジカルコントローラーにより、直感的なビートメイキングが可能です。
TR-6Sには、往年のTR-808やTR-909、TR-707、TR-727、TR-606などのサウンドが詰まっています。
これに加えて、ユーザーサンプルやFMサウンドと組み合わせ、オリジナリティ豊かなリズムキットを作成できます。
リズムプログラミングはTR-RECスタイルを踏襲し、リアルタイムのレコーディングやサブステップ、モーションレックなど現代的な機能も搭載。
あらゆるジャンルに対応するプログラミング機能を提供します。
TR-6Sには高品質なエフェクトが豊富に搭載されており、コンプレッサーやイコライザーからリバーブ、ディレイ、モジュレーションエフェクトまで幅広い空間系エフェクトが利用可能です。
多用途で便利な1台で、高品質のUSBオーディオ/MIDIインターフェース機能も搭載。
モバイル環境やミニマルプロダクション環境に最適で、単三乾電池またはUSBバス電源で駆動可能。
どんな場所でもアイデアを思いつくままに音楽に没頭できます。
KORG(コルグ)
NAUTILUS-61

限りなく表現を広げる、究極の音楽創造ツール!
「NAUTILUS」は、圧倒的な表現力を誇る9種類のサウンド・エンジンを内蔵したワークステーション型シンセサイザーです。
これまでにない高度な音楽制作を可能にし、ライブパフォーマンスでも驚きのパフォーマンスを発揮します。
そのユーザビリティの高さとタッチ操作可能な大型カラー液晶ディスプレイは、直感的な操作を実現し、創造力を解き放ちます。
61鍵のナチュラル・セミ・ウェイテッド鍵盤は、中程度の重さで演奏しやすく、ベロシティ対応により細かな音の変化を表現します。
さらに、ハーフダンパー対応のサステインペダルやエクスプレッションペダルの接続によって、演奏の表現力をさらに広げることができます。
NAUTILUSの音源部には、アコースティックピアノ、エレクトリックピアノ、オルガン、VPM/FM、位相変調、名機モデリングなど、多彩なオシレータータイプが搭載されています。
最大同時発音数は40から200ボイスで、音切れの心配もありません。また、オープン・サンプリング・システムを採用しており、プログラムやコンビネーション、シーケンサーなどのモードに関係なく、外部オーディオのサンプリングや本体演奏のリサンプリングが可能です。
さらに、USBメモリーやさまざまなサンプルフォーマットの読み込みにも対応しています。
「NAUTILUS」は、限りなく表現を広げるための究極の音楽創造ツールです。そのダイナミックス・ノブやクイック・アクセス・ボタンを使い、音色や音量の変化を瞬時にコントロールできます。
さらに、USB Ethernetアダプターを使用することで、大容量サンプルの高速転送も可能です。
Volca Keys

Volca Keysは可愛いコンパクトなルックスのアナログシンセサイザーになります。
16トラック・ステップシーケンサーを内蔵し、どこか懐かしい音を出すことができるので、アナログ感の音を好む人には嬉しいシンセサイザーでは無いでしょうか。
コンパクトなサイズで、持ち運びが簡単にでき、乾電池でも駆動するので野外にも持ち運ぶことができます。電池での駆動は10時間ほどもつため、長時間のライブでも動作が止まることなく使用できます。
また、スピーカーを本体に内蔵しているため、どの場所でも音を鳴らすことが可能になります。
monotron DELAY

モノトロン DELAYは、アナログ・シンセサイザーの新たな進化です。
そのコンパクトなサイズにもかかわらず、驚くほど多彩な機能が搭載されています。
リボン・コントローラーを駆使して、アナログならではのサウンドを探求しましょう。
ヘッドホン・ボリュームの調整で、どこでも音楽制作の醍醐味を味わえます。
AUXインプット(3.5mmステレオ・ミニ・ジャック)を使用して、外部音源を簡単に組み込むことができます。
そして、その独自のディレイ機能は、まるでアナログ・テープ・エコーのようなサウンドを生み出すことができ、ピッチの変化も楽しめます。
さらに、LFO波形の多彩な選択肢とデューティー比の調整で、クリエイティブなサウンドを手に入れることができます。
このモノトロン DELAYは、コルグの伝説的なMS-10やMS-20から受け継いだVCF回路を誇り、音に深みと表現力を与えます。
コンパクトながらも小型スピーカーを搭載しており、どこでも演奏を楽しむことができます。
さらに、外部入力端子を使えば、デジタル・オーディオ・プレーヤーなどの音源と組み合わせて、新しい音楽の可能性を追求できます。
モノトロン DELAYは、音楽制作とパフォーマンスの新たな次元を切り拓くパートナーです。
minilogue xd

minilogue xdは、ハイブリッドシンセサイザーになり、37鍵のコンパクトモデルになっています。
背面がウッド調のデザインになっているため、大変オシャレでテンションが上がります。
ツマミもたくさんあり、機能面では困ることはないでしょう。
エフェクトも充実しているため、独自の音色を作り込むこともできます。
作れない音がないほど、無限の可能性を秘めたシンセサイザーではないでしょうか。
microKORG

37鍵盤の小さなボディのアナログシンセサイザーになります。
個性あふれる音作りを追求した本格的なシンセサイザーで、8タイプのオシレーター・アルゴリズムを元に、自在にサウンド作成をすることができます。
アナログが好きな方には、とっておきのシンセサイザーになるでしょう。
MONOLOGUE

minilogueをベースにしたMONOLOGUEは、コンパクトな25鍵タイプのアナログシンセサイザーになります。
小さなボディからは想像もつかない音色を作り出すことができ、電池で駆動するため、持ち運びが便利な構造になっています。
多様な種類の色を選べるため、好みの色を選んでみましょう。
色のバリエーションは、ブラック・ブルー・ゴールド・レッド・シルバーの全5色になっていて、背面はウッド仕様になっているので、高級感あふれる外観になっています。
MOOG(モーグ)
Matriarch

MOOG(モーグ)の4音パラフォニック・セミモジュラー・シンセサイザー、Matriarchは、セミモジュラー・アナログシンセサイザーの頂点に位置します。
このシンセサイザーには、4つのボイスを持つパラフォニック機能があり、アナログシンセサイザーだけでなく、ステップシーケンサー、アルペジエーター、ステレオラダーフィルター、ステレオアナログディレイも組み込まれています。
Matriarchは、モノ、デュオ、および4音パラフォニックモードを活用して、シーケンスやパフォーマンスを幅広く楽しむことができます。
ステレオアナログディレイには、豊かなフィードバック効果があり、クラシカルなピンポンディレイを実現しています。
このシンセサイザーは、90のモジュラーパッチポイントを搭載しており、パッチングを通じて複雑な音の組み合わせや独自のサウンドを作り出すことが可能です。Matriarchはセミモジュラータイプであり、パッチングなしでも音楽制作が楽しめますが、3.5mmのパッチケーブルを使用して90のパッチポイントにアクセスすることも可能です。
モジュラーアナログシンセサイザーとして、MatriarchはBob Moogのオリジナルな回路設計に基づいており、100%アナログ信号パスを持っています。
その結果、ダイナミックで多彩なサウンドが実現され、ビンテージステレオラダーフィルターやデュアルエンベロープジェネレーター、ステレオアナログディレイ、ステレオVCAなどが組み合わさり、多次元的なサウンドを提供します。
Matriarchはまた、直感的な256ステップシーケンサーを搭載しており、最大4つのパラフォニック・ボイスを組み合わせて豊かなハーモニックを作り出すことができます。
また、外部音源のプロセッシングにも適しており、他のMoog製品やEurorackモジュラーシステムと組み合わせて使用することができます。
Matriarchは、ステージやスタジオでの幅広い音楽制作に対応する、強力で柔軟な電子楽器です。
Subsequent25

MOOG(モーグ)のパラフォニック・アナログシンセサイザーは、その高度な機能と柔軟性によって注目を集めています。
Subsequent 25 Editor/Librarian Softwareを利用することで、プリセットの管理と共有が簡単に行えます。
このシンセサイザーは多彩なコントロールオプションを提供しており、音楽制作の可能性を広げます。
ピッチベンドとモジュレーションは、使いやすいホイールで調整可能です。
また、3つのCV-INポート(ピッチ、フィルター、ボリューム)と1つのGATE-INポート(キーボード)を備えており、外部機器との連携がスムーズに行えます。
エフェクトとしてはMultidriveを搭載しており、サウンドに独自のキャラクターを付け加えることができます。
また、モノラルの音声入力と出力をサポートし、クリエイティブな音楽制作に必要な接続オプションを提供します。
MIDIに関しても十分な機能を備えており、INおよびOUTポートに加えて、USB-MIDIポートも備えています。
これにより、他のMIDI機器との連携やコントロールが簡単に行えます。
本体のサイズは幅約51.5cm、高さ約17.5cm、質量約7.26kgとコンパクトで、スタジオやライブパフォーマンスでの移動も容易です。
さらに、広範囲の電源対応(110V AC – 240V AC)により、国際的な使用にも対応しています。
MOOGのパラフォニック・アナログシンセサイザーは、その洗練されたデザインと卓越した機能性により、プロの音楽制作者やエレクトロニックミュージック愛好家にとって理想的な選択肢と言えるでしょう。
MOTHER 32

Moogの最初のテーブルトップ・セミモジュラーシンセ、”MOTHER 32″は、メインモジュールが脱着可能で、ユーロラックにも適応可能です。
パッチングなしでも直ちに音作りや音楽制作が可能なセミモジュラー設計を採用しています。
以下は主な特徴です。
64の異なるシーケンスをメモリーに保存可能な電圧制御32ステップシーケンサー
電圧制御レゾナンス付きのローパス/ハイパスMoogラダーフィルター
外部オーディオ入力により、他の機器からのオーディオ信号の加工が可能
Moogオシレーターにはパルス波とノコギリ波の出力が備わっています
5ピンコネクターのMIDI入力とMIDI-to-CVコンバーター機能
32のパッチポイントを持つパッチベイ(5本のパッチケーブルが付属)
2基の電圧制御ミキサーを搭載
Moog Werkstatt 01、Minotaur、および他のシンセサイザーとの組み合わせが可能
メインモジュールは脱着可能で、ユーロラックケースに取り付け可能
2ティアまたは3ティアのキット(別売)を使用して、2基または3基のMother-32をマウント可能
これらの機能を1台で網羅しているため、ユーロラック初心者にとって最適な選択肢となっています。
NOVATION(ノベレーション)
Bass Station Ⅱ

今もなお人気の高いアナログシンセサイザーのBass Station Ⅱは、ベースサウンドはもちろんリードサウンドやアルペジオサウンドなども奏でることができます。
片手で音を混ぜならが作るサウンドは、どんな場面でも簡単に使うことができ、持ち運びも便利なためいつものお供として使ってみてはいかがでしょうか。
MiniNova

新テクノロジー”VocalTune”を搭載した、ミニ37鍵盤仕様のパフォーマンスシンセサイザーのMiniNovaは、UltraNovaと同じシンセエンジンを採用し、256の即戦力の音色プリセットを装備しました。
このサイズ感からは想像できないくらいのパワフルなサウンドを体感してください。
小規模なイベントでの演奏や、音楽制作に最適な1台となること間違いなしです。
TEENAGE ENGINEERING
OP-1

ポータブルシンセサイザーのOP-1は、内蔵スピーカーをと内蔵マイクを備えたシンセで、FMラジオを使って気軽に使えるサンプラーにもなります。
シンセやドラム、シーケンサーやテープ、ミキサーといったモードを選び、曲のパフォーマンスやアイデアを次々提案してくれるため、飽きない曲作りをすることができます。
AKAI
EWI5000J

定番のウインドシンセサイザーEWI5000Jは、PCM音源を採用していて既存の音を録音し、それを再生させることで音を発生させます。
ですから、生楽器の良さをそのまま再生させることができるので、非常にリアルな音を出すことができます。
音色の幅が広がり、トランペットはもちろん木管楽器やピアノの音色などさまざまな音を奏でることができます。
NORD
Nord Stage 3 Compact

73鍵盤のキーボードシンセサイザーNord Stage 3 Compactは、豊富なエフェクトや技術を集結したシンセサイザーになります。
暗いライブハウスなどでも鮮明に確認できる有機ELディスプレイにより、直感的かつ柔軟にライブ・パフォーマンスを可能とします。
新しく搭載されたソング・モードでは、プログラムをリスト内の個々のソングに簡単にグループ分けすることができます。
各ソングには最大で5つの異なるプログラムを登録することができるので、状況に合わせて瞬時にアクセスすることが可能となります。
ARTURIA(アートリア)
MicroFreak

鍵盤数25のコンパクトシンセサイザーMicroFreakは、10種類を超える音源方式に対応し、最大4ボイスのオシレータを搭載しています。
USBやMIDIなどのコネクターを装備しているので、主要な機材ともつなぐことができ作曲や録音を身近なものにしてくれます。
今後もオシレータを拡張していくので、楽しみに待ちましょう。
IK MULTIMEDIA
UNO Synth Pro Desktop

NO Synth Proは、本物のアナログ・サウンドを追求したシンセサイザーで、3基のアナログ・オシレーター(PWM、シンク、FM、リング・モジュレーションを連続可変)とデュアル・フィルター(SSI製の2ポール/4ポールのローパス・フィルターとオリジナルUNO Synthの2ポールOTAマルチモード・フィルターを各1基搭載)を備えています。
さらに、フルADSRエンベロープx2、LFOx2、16スロットのモジュレーション・マトリクスを備え、柔軟な変調によるサウンドデザインが可能です。256種類の編集可能なプリセット、64ステップ・シーケンサー、アルペジエーターも搭載し、充実のプリセットとシーケンサーを提供します。
さらに、アナログ・オーバードライブ回路と3系統(モジュレーション、ディレイ、リバーブ)のデジタルエフェクト(合計12種類)を使用可能です。
UNO Synth Proは高度な拡張性も持ち、バランス・ステレオ出力、ヘッドフォン出力、USB端子、MIDI IN / OUT 端子、CV / Gate IN / OUT 端子、AUDIO IN 端子が備わっています。
そのため、外部信号をフィルターやエフェクトの前段、またはアウト端子にルーティングすることができます。
これにより、本格的なアナログサウンドを生み出すだけでなく、さまざまな拡張性と柔軟性を提供し、伝統的なシンセサイザーの音色を再現するだけでなく、新しい音色の創造も可能となっています。
BEHRINGER
TD -3-AM

TD -3-AMは、アナログベースラインを演奏させることができるシンセサイザーになります。
ビートにすぐに合わせることができる音色は、曲を作るときにもすぐにマッチするため、曲の完成がものの数秒で出来上がります。
高度なアルペジエーターなどの機能も装備しているため、直感的に音を作り込むことができます。
今すぐビートと合わせて TD-3-AMを使い、トラックメイキングしてみてはいかがでしょうか。
YAMAHA
MOXF6

MOXF6は、61鍵盤のキーボードシンセサイザーになり、リアルなピアノ音に加え、エレクトリックピアノ、菅弦楽器やドラムなどの高品位でクリアなサウンドを収録しています。
また、ピアノを弾く感覚でドラムやギター、ベースなどの音を構築させることができるので、さまざまなジャンルへの対応を可能とし、ライブパフォーマンスでも十分に力を発揮することができます。
USBオーディオMIDIインターフェース機能を使うことで、オーディオとMIDIのやりとりも可能になります。
Pioneer DJ ( パイオニア )

TORAIZ AS-1
Dave Smith Instruments社のProphet-6を元にした、モノフォニック・アナログ・シンセサイザーが登場しました。
このシンセサイザーは直感的なユーザーインターフェイスと高度なパフォーマンス機能を備え、演奏中にアイデアをそのまま表現することが可能です。
主な特徴は以下の通りです。
アナログ・ディスクリート回路をベースにしたトゥルー・アナログサウンドを提供する、Dave Smith Instruments社のProphet-6のサウンドエンジン。
2基のVCO(可変三角波、鋸(ノコギリ)波、矩形波)を搭載したシンセシス・エンジン(2VCO、2VCF、1VCA、2EG、1LFO)。
フルプログラマブルでありながらも、スピーディーなアクセスが可能な音色。
495種類のファクトリー・プリセット・プログラム。
プログラムごとに独立した64-STEP SEQUENCERのパターンを内蔵。
Prophet-6のデュアル・エフェクト・エンジンを搭載。
タッチパッド式のKEYBOARDで即座に演奏可能。
SCALE MODEを活用し、音楽理論の知識がなくても感覚的に新しいフレーズを作成可能。
マルチアサイン可能なタッチパッド式のSLIDERにより、7種類のパラメーターを操作。
ARPEGGIATORを搭載。
MIDI経由でTORAIZ SP-16に接続すると、より複雑なパターンの作成が可能。
このシンセサイザーは、Prophet-6の伝統を継承しつつ、直感的な操作性や豊富な機能を備え、音楽制作において幅広い表現が可能です。
Gamechanger Audio ( ゲームチェンジャーオーディオ )

MOTOR SYNTH MKII
世界で唯一のメカニカルシンセサイザー、MOTOR SYNTH(モーターシンセ)は、独自のモーターオシレーターエンジンを搭載したユニークなシンセサイザーです。
8つのエレクトロモーターにより瞬時に回転速度を変化させ、その動きから音を生成します。
モーターによる波形作成の独自性から、アナログやデジタルにはない唯一無二のサウンドを提供します。
Gamechanger Audioのエンジニアによって開発され、サウンドシェイピング機能を搭載しており、クラシックなシンセからリアルな楽器まで幅広いサウンドを生成できます。
MOTOR SYNTH MKIIは、3種類の光学式波形(Sine、Saw、Square)と電磁誘導波形(M)から選択可能な2ボイスのオシレーターを搭載しています。
各ボイスはVOLUMEやSCALEなど5つのコントロールを持ち、幅広いサウンドメイクが可能です。
デジタルオシレーターと自在なボイスルーティング機能も搭載されており、完全に独立した第3のDIGITAL VOICE(DCO)や調整可能な4音ポリフォニーを利用できます。
バーチャルアナログオシレーターやウェーブシェーピング付きのノイズエンジン、複数のルーティングオプションにより、自由自在なボイスルーティングが可能です。
パフォーマンス・インターフェイスは、8つのキーパッドや4つのロータリーピッチエンコーダーを備え、CLUTCH機能によりパラメータ操作を一時的に無効化することができます。
アルペジエーターや内部ノートシーケンサーエンジン、モーションRECエンジンなども搭載されており、豊富な機能を提供しています。
ボイスセクションでは、2ボイスのオシレーターが3種類の光学式波形や電磁誘導波形から選択可能です。
各ボイスはVOLUME、SCALE、WAVE、AMP ENVELOPE、PITCH ENVELOPEのコントロールを備え、AMP ENVELOPEには複数のモード(ADSR、AD、AR、DADSR、ADSHR)が選択可能です。
ピッチエンベロープシステムを活用し、モーターオシレーターのピッチを細かくコントロールできるACCELERATIONとBRAKE機能も搭載されています。
アナログフィルターは、各モーターボイスに完全に独立したアナログフィルターを備え、24dBローパス、12dBバンドパス、12dBハイパス、24dBオールパスの4つのフィルターモードを提供します。
アナログドライブ回路やキートラックエンジンも搭載され、フィルターの柔軟な制御が可能です。
モジュレーションセクションでは、2つのデスティネーション・スロット、MODのシェイプセレクター、独自に調整可能なクロックソースやサブディビジョンを備え、柔軟なモジュレーション制御が可能です。
また、MIDI&CVコントロールも充実しており、ノートとクロックの情報の送受信や複数のMODホイール、CV入力、トリガー入力などが利用できます。USB経由でMIDI入出力やMICRO SDカードへのファイル転送が可能です。
おすすめシンセサイザーまとめ
いかがでしたでしょうか。
好みのシンセサイザーは見つかりましたか?
はじめに紹介したシンセサイザーを選ぶときの注意点で、購入したいシンセサイザーが見つかったときには、一度楽器店などで試奏させてもらうのも良いかもしれません。
なかなか楽器店に行けないという方は、スペックなどを確認し、自分が想像する演奏ができるのかどうか、慎重に調べて購入を検討してみてください。
高価な値段のシンセサイザーが多いため、変えが効かないので、一生のパートナーを選ぶつもりでじっくりと考えてみてはいかがでしょうか。
それでは、また。
Recent Posts