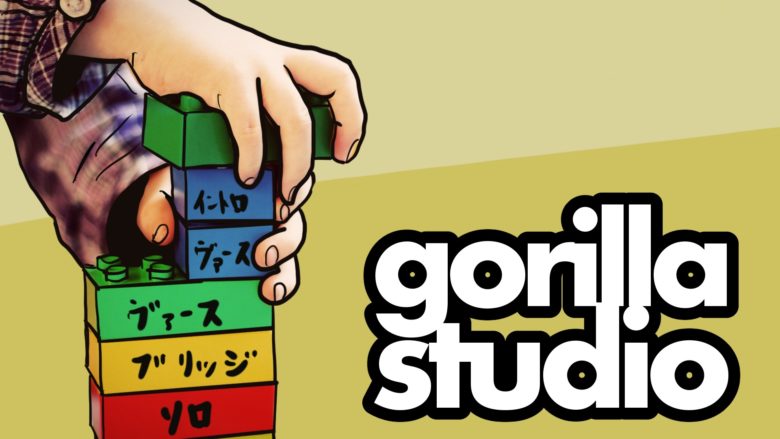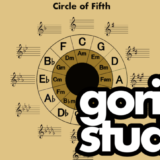はじめに
みなさんは、曲や歌を作るときにワンパターンになってしまったり、曲を作ったのは良いけれども、Aメロからサビまでが同じ感じのメロディーになった経験はありませんか?
それは、コード進行をうまく使っていないからなのです。
うまく使えていないから、同じような曲調になったりするのではないでしょうか。
作曲する時に、一番重要になってくるのは、AメロからBメロにつなげる時に、変化をもたらせ、Bメロからサビに移る時も、変化をもたらせるようにコード進行を組み立てていきます。
さあ、みなさんも曲の構成を考えながら、たくさんの曲を作って世に発表していきましょう。
曲の構成について
どんな曲であっても、コード進行にそって曲が構成されています。
ただ、何も考えずに構成を作ったとしても、その曲を聴いた人が感動したり、心に残る名曲にすることはむずかしいでしょう。
聴いた人に作った曲を曲として感じてもらうためには、曲の構成をしっかりと考え、ストーリーを作っていくことが重要になってきます。
ここでは、さまざまな構成を考え、ドラマチックに曲が流れるように、パターンを作っていきます。
それでは見ていきましょう!
ブロック構成
まずは、ブロックごとの構成を確認していきます。
イントロ
文字通り楽曲のはじまりの部分になります。
キーやリズム、テンポや曲の雰囲気といった、楽曲の主な構成要素がすべこのイントロで表現されます。
いろんな曲を聴いてみると、ヴァース(Aメロ)やコーラス(サビ)からヴォーカルを取り除いたものがイントロになっていることが多いです。
ヴァース(Aメロ)
曲の世界観を形作るところになります。日本ではAメロと言われている部分ですが、ここから曲の物語がスタートします。
一般的な楽曲には複数のヴァースがあり、メロディは同じで歌詞が異なることが多いです。
ヴァースを良いメロディにしないと、コーラス(サビ)まで聴いてもらう事ができないかもしれません。
コーラス(サビ)
いわゆるサビにあたる部分で、楽曲が一番盛り上がる場所になります。
コーラスが良ければ、その曲を一瞬で好きになります。
また、一番伝えたいことをこのコーラス部で表現します。
なので、歌詞の一部が楽曲のタイトルとなっているケースが多いのではないでしょうか。
ブリッジB (Bメロ)
一般的なポップスの曲では、なくてはならない存在です。
Bメロを抜いた曲もありますが、やっぱりBメロがないと、コーラスに向かって盛り上がりに欠けますよね。
ブリッジC(Cメロ)
ブリッジCは、日本ではCメロにあたるぶぶんです。
本来はBメロもCメロもブリッジでくくられますが、ややこしくなるので、分けておきます。
ソロ
ソロは間奏になります。
楽器のソロが入ったり、少し静かにして、そこからコーラス(サビ)に向かって盛り上げていく部分になります。
エンディング
エンディングは、曲の終わり部分になります。
終わり方も曲それぞれで、フェードアウト(音が少しずつ小さくなっていくこと)して終わったり、一つの楽器が静かに鳴ったりと、終わりを表現する部分になります。
エンディングが良ければ、また聴きたいと思うようになるので、最後まで作り込みましょう!
曲の構成を考える
曲の構成を考えることは、曲作りに大変重要になります。ここからは曲の構成を考えていきましょう。
パターン1
イントロ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ソロ→ブリッジC→サビ→エンディング
よく聞くパターンになります。JーPOPなどはこのパターンが多いです。ソロの後にCメロ(ブリッジC)が入っているのが特徴になります。
パターン2
イントロ→ヴァースA→サビ→ヴァースA→サビ→エンディング
とてもシンプルなパターンになります。Bメロがないパターンで、サビで変化をつけたり、Aメロ(ヴァースA)の歌詞を変更したりすることで柔軟に対応することもできます。
パターン3
サビ→イントロ→ヴァースA→ブリッジB→サビ→ソロ→ブリッジB→サビ→エンディング
サビから入るパターンになります。サビにインパクトがあれば、そのまま聴いてもらえます。サビが印象に残れば、リピーターが増えるかもしれませんね。
パターン4
Aメロ→Bメロ→サビ→Aメロ→Bメロ→サビ→サビ→エンディング
Aメロからいきなり曲が流れるパターンです。イントロがない分、サビに行くまでの展開が早いため、曲に聞き入ってサビにつなげることがキモとなります。
Recent Posts